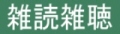副題は「戦後の日本文化を歩く」。
ジャズの受容を軸に日本の戦後文化を論じた『戦後日本のジャズ文化』は、この数年間で最も刺激的なジャズ書だった。サントリー学芸賞を受賞。
なかでも「挑発的に論じた」ジャズ喫茶に関する章がとくに面白く、反響もこの部分がいちばん大きかったようだ。
そこで著者モラスキー氏は、より多角的にジャズ喫茶を研究しようと、2007年から1年間かけて全国のジャズ喫茶調査にとりかかる。
その成果は、昨年WEBちくまに連載されていたが、その後の追加取材や改稿を行って1冊にまとめられたのが本書である。
じつは、おれは大阪方面の取材に数軒同行している。(この日とかこの日とか)
傍で話を聞いていたり、おれも割り込んだり。
前書で批判的に論じられていたは「硬派」(私語禁止、ひたすら修行僧のように聴く)の店だったから、「多角的に論じる」となると、色々な営業形態を全国規模で調査する、歴史的には10年区分の変遷をもっと精密に調べる……という方向かなと想像していた。
本書を読んで驚嘆。「多角的」といっても、そんな常識的なレベルではなかった。
むろん、全国調査で色々な店が紹介されるが、単に営業形態のみならず、店主の性格、客側の視点、立地(「売春地帯のジャズ喫茶」なんて視点は想像もできなかった※)、広告やマッチのデザインなど、考察はまさに多面的。歴史的にも、戦前まで遡り、基地の問題、朝鮮戦争やベトナム戦争の影響まで(その意味で沖縄の追加取材は大きい)精査されている。
さらに、前書同様、周辺文化との関係も考察されている。
文化論、現代史、考現学(社会学)、ジャズ論……となるほど「多角的」とはこういうことであったかと感嘆する。
また、この本が決して堅苦しくないのは、ジャズ喫茶を巡る旅行記としても面白いからで、特に今治というジャズの穴場を「発見」する件りは爆笑ものである。
新時代のジャズ喫茶に希望を託して終わる構成もいいなあ。
おれもジャズ巡りに出かけたくなってくる。
モラスキーさんもまだ行きたいところが「山ほどある」という。
どこかの雑誌の企画で連載してくれないかなあ。
で、おれも、本書に未記載の店と視点を追記。
・高知の「木馬」……ここは歴史的にも古く、今も昼の喫茶営業が続いている本格派。2階がライブスベースになっている二重構造である。
・宮崎の「ライフタイム」……この店はまだ行ったことがないが、ジャズファンもミュージシャンも口を揃えて絶賛するのがマスターの作る「料理」である。それも「冷や汁」とか「キズシ」とか、魚料理など、どちらかといえば割烹メニューである。ジャズよりも料理の腕で全国に知られるとは。つまり「味覚から」ジャズ喫茶を論じる視点もあるかな、ということである。
※「売春地帯のジャズ喫茶」の注目は熱海の「ゆしま」である。熱海へは70年代後半からの数年、SF作家クラブの旅行で毎年行ったけど、知らなかったなあ。ともかく、周辺で「人類最古の職業」が営業をやめたのにジャズが残ったというのは奇跡的だ。荷風○人さん、いっしょに見物に行きませんかと誘いたくなるなあ。
※※ついでに一言。158頁に出てくる「ありんこ」のワニ……これは出典はスイングジャーナルのレコード評のオマケ(0.5点)マークをアレンジしたものだと思う。
(2010.3.14)
人気の「落語ミステリー」シリーズの4冊目である。
相変わらず、梅駆こと竜二は師匠から殴られたり、兄弟子からはいじめられたり、さんざんの生活だが、ついに内弟子期間が終わる。
落語ミステリーといいつつ、殺人も犯罪もない。パズラーでもない。初期の「謎」に較べると、今やその謎は「なぜ師匠の機嫌が悪いのか」程度の他愛ないものになっている。その分、落語界での諸事項が細部まで描かれて、年季明け前後の雰囲気が伝わってくる。
あほらしき(しかしちょっと泣かせることもある)事件の連続で、さらに今回は梅寿が人間国宝に!?
タイトルが「仔猫」「兵庫船」「皿屋敷」「ひとり酒盛」など、好みのネタが並んでいるのも嬉しいね。
独り立ちした梅駆の活躍やいかに……
で、今「小説すばる」に連載中の最新作は「ファイナル・シリーズ」と銘打たれている。
5巻目が最終になるのか?
もしそうであるとして、最終話のタイトルがどうなるのか、ともかく色々な期待が高まる。
(2010.3.14)
副題は「江戸の仇をアラスカで討つ人」である。
おれはこの28年間、毎日のように、ひとつはレンガでハゲ頭をガツンと殴り、もうひとつは巨根をギロチンで切断してやる妄想にとらわれる……そこまで憎みつづれている下等物件が2個ある。
われながら執念深いなと思うが、おれの受けた精神的被害はそれほどひどいものであり、しかし、むろん妄想を実行するには、おれはそれを抑制する一応「理性」も持ち合わせているのである。
これは精神的には負担でもある。
自分の仕事の邪魔にもなるのは確かだ。
で、参考になるかなと本書を読んでみた。
ここに出てくる症例(小説からの事例が多く、ディックなどSFも色々)は、あまりに非現実的で参考にならず。同窓会を主催して同級生皆殺し(いじめへの報復)を図った事例は面白いけど。
最後の方で、やっとおれに近い症例が出てきたが、強いていうなら「脅迫神経症」のずっと手前のようである。
最終的には「苦笑の効用」にしたがうしかないか。
確かに上記2物件のひとつ「巨根」の方は、狭い業界の中でアホと認知されているしなあ。しかし、もう一個のチンカス三百代言は、やっぱり「苦笑」で片づける気分にはならんらかなあ。
書くしかないわけか。
ともかく、執念深いのである、おれは。
(2010.3.14)
日下三蔵編『日本SF全集2 1972〜1977』(出版芸術社)
日下三蔵氏の編集になる『日本SF全集』の第2巻。
これは宣伝であります。
70年代半ばから80年代はじめにかけての作品を収録。
年齢的には野田昌宏さんから山尾悠子さん(なんと蠱惑的なお写真!)まで、わが同世代の諸君中心に、代表的な短編が集められております。
(ごく一部ではおれの最高傑作ではないかという声がないではない)拙作「アンドロメダ占星術」も収録されております。これ以外は、ともかく傑作ぞろい。
ちと高いから、ぜひともお買い求めをとはいいにくい。
その後の巻も継続して発行されますよう、最寄りの図書館にリクエストしていただければありがたく、謹んでお願い申し上げます。
(2010.3.14)
帯に「おれは座頭市だ」……そりゃそうだが、「座頭市はおれだ」ではなかったのだ。
ややこしい表現だが、今までのカツシン像が覆される。
勝新太郎の評伝……それも映画作りに限定した評伝である。
カツシンといえば、その豪傑ぶり、とくに取り巻きを引き連れての豪遊で知られていて、それに憧れて破綻したのが水原弘……いや、カツシンも破綻したんだけど、役者がちがった。そりゃ、歌手と役者だからなあ。
が、カツシンは(後半生においては)主演俳優に加えて、脚本家?であり監督であり編集者でありプロデューサーであり(勝プロの)経営者でもあった。
映画製作の全工程に関わったのである。
その映画作法は、『警視−K』から始まり、テレビの「座頭市物語」「新・座頭市」シリーズ100本は、シナリオ無視(なし)、その場その場で場面を作っていく方法で作られたという。
この過程でカツシンは「おれは座頭市だ」になってしまうのである。
この方法が、その後『影武者』で黒澤明との衝突を生むことになる。(そして、カツシンの黒澤批判はある程度当たっていると思う)
この「真相」はほとんど知らなかった。
おれはテレビの座頭市シリーズをまったく見ていなかったからである。
カツシン監督作品を見たのは、最後の『座頭市』(1989)で、何ヶ所かの映像美に感心したがドラマとしては面白みを感じなかった。
その理由も本書で氷解。
岡本喜八が監督した『座頭市と用心棒』がいまひとつだった事情もよーーーくわかった。
大監督との作品が不発な事情もよくわかった。山本薩夫『座頭市牢破り』も勅使河原宏『燃えつきた地図』もそう。(ただし、市川昆『銭の踊り』は傑作と思う)
そして、やっぱり、三隅研次、田中徳三の凄さを再確認する。
こまかくコメントしたいことは山ほどあるが、カツシンが映画監督として「天才」だったかとなると、微妙なところだなあ。役者としてトップスターになれなければ「監督」もやれなかったはずだし、まして「脚本無視」は(成功しても)変則的な作品にしかならなかったわけだし。
それでも、テレビのシリーズを見てみたくなる。
著者・春日太一氏は1977年生まれ。カツシンは1931年生まれである。
おれの年齢に置き換えると、おれが大河内傳次郎かバンツマの評伝に挑むようなものか。
そう考えると、大映京都撮影所のスタッフを丹念に取材されている姿勢に敬服する。
ギリギリで間に合ったというところだ。
できれば雷蔵も、さらに拡大してチャンバラ全体まで論じていただきたい。
※余談。
おれはカツシンのデビュー作『花の白虎隊』を小学時代に見ている。ただし、主演の雷蔵もカツシンも記憶にない。白装束で行進する場面しか覚えていない。
だが、翌年に見たカツシンの主演作『かんかん虫は歌う』はよく覚えている。現代劇。「かんかん虫」というのは船の修理ドックで外壁こびりついた貝やサビを金槌でカンカン叩いて落とす修理工のことである。ロープにぶらさがってカンカンやってたカツシンを今も覚えている。その存在感は当時から雷蔵の上を行ってたのである。
(2010.3.28)
勢いの感じられる福田和代さんの最新長篇である。
おれは自分のHPで時々「本気にしないように、エシュロンくん」というフレーズを入れることがある。これは、自分の身辺のことをちょっと誇張して書いた時などに、「余計な詮索はしないでくれよ」という、見知らぬ誰かへのメッセージである。
斎藤貴男『プライバシー・クライシス』や産経新聞特別取材班『エシュロン』が出てから約10年、特にエシュロンについてはあまり話題にならなくなっている。こういう時の方がかえって怖いのである。
本HPも始めてから14年……これはインターネットが日常に溶け込んだ期間でもある。ネットはますます便利かつ複雑になっているが、おれは、結局14年前にスタートした時のままの、古めかしいスタイルで続けている。タグ手打ち、エディターで書いているんだからね。
ツイッターは遠慮、クラウド・コンピューティングは(利便性は理解しているが)不気味で手が出せない。
ま、臆病なのである、おれは。
『オーディンの鴉』は、この10年間に根付いたネット社会の「潜在的な恐怖」を描いたサスペンス小説の傑作である。
防衛問題で家宅捜索を受ける予定だった政治家が飛び降り自殺する。疑獄に発展するのを防ぐための自殺に見えたが、「私は恐ろしい」という遺書を残していた。
主人公は東京地検特捜部の検事である。
捜査を進めるうちに、その政治家がネット上で奇怪な攻撃を受けていたことがわかってくる。匿名による世論誘導だけではなく、自販機の監視カメラによる画像やカード情報までが恣意的に使われている。
検察組織のどこかにも捜査を中止する空気が感じられ、やがて「監視」の眼は主人公の日常(家族)にまで「警告」の形で影響しはじめる……。
物語の構造はオーソドックスで、脇役(隠然たる力を誇示する右翼の大物とか、手をさしのべてくるオタクとか)の配置もきちんとしている。前半で特捜の内部(捜査手順だけでなく、検事の部屋の配置など)が詳しく描写されていて、それが後半の急展開・急拡大の緊迫感とリアリティにつながって、ともかく一気に読ませる。
ミステリーなので、お話の紹介はしないが「決着」も見事である。
なによりも監視社会の潜在的な恐怖感を物語のかたちにした筆力はたいしたものだ。
臆病なおれがビクビクハラハラしながら本を手放せなかったんだからね。
(2010.4.13)
小説すばる5月号を読んで(たいしたことではないが)色々思うところがあったので列記。
送っていただく本は丹念に読ませていただくことにしている。
なぜか(10年ほど前からの5年間、文芸家協会の某委員として小説誌を全部読んでいた時期があるせいか)「小説すばる」はいつも送っていただいている。
一頃、常磐雅幸『真ッ赤な東京』以外はほとんど興味が持てない時があったが、面白そうなのは読ませていただいている。
今号、面白いのが色々あった。
・注目の連載、佐々木俊尚『電子書籍キンドルは何を壊し、何を創るのか』が完結、たぶん近いうちに集英社新書で刊行されるのではないか。作家(小説家)という職業がますますしんどい稼業になり、編集者の仕事がますます過酷になることが実感できる。
・万城目学氏の新連載。「まきめ・まなぶ」と読むことを初めて知った。「リンゴの唄」や「悲しき口笛」を聴いた世代は「まんじょうめ」と読むわなあ。作家も作曲家も姓の読み方はともに「本名」なのであった。お詫び申し上げます。といっても、アタマのなかでマンジョウメと読んでいただけで、発声はしてないから、特に誰かに迷惑かけたわけではないけど。
・福田和代さんの新連載『怪物』……これはSFか? 「水」が凄いことになりそうな。
・田中啓文……上燗屋、よろしいなあ。
・金原瑞人氏のティプトリー考察は鋭い。
……と色々あるが、なんといっても突出しているのは、301頁の3枚ほどのコラムである。
「特別料理」という、思い出に残る手作り一品について色々な人が書くコラム。
今号は両角長彦氏が登場。
「エサと料理の境界とは」という根元的問いかけからはじまって、驚天動地の結末へ。驚いたのなんの。たった3枚に「食文化」の本質が濃縮されている。
両角氏はミステリー、SF、冒険小説で期待の新人だが、こりゃ、さらに笑いの分野でも期待できるのではないか。好漢の健筆を祈る。
雑誌というのは、こんなコラムがひとつあるだけで、十分満足できるのである。
安いぞ。出来れば買って、無理なら301頁の立ち読みを。
(2010.4.19)
第8回ジュニア冒険小説大賞受賞作。
中世?の日本、ナユタ少年は親のいない(あるいは預けられた)子供たちだけの住む山中の家で暮らしていた。 焼け落ちる家と母に手を引かれての逃走……ナユタにはそれしか記憶がない。
世話人はセンジュという男。
ある日、その家は何者かに襲われ、床下に隠されたナユタ以外、誰もいなくなった。仲間の子供たちはどこへ連れ去られたのか。
ナユタは病んだ左目を布で覆ったまま育った。センジュは「本当にどうしようもなくなった時は左目を開けろ」といいつけていた。
ナユタは左目を開ける。
と、そこには見たこともない別の世界が広がっていて、モノトーンの世界に黄金色に輝く蝶が舞うのを見る。
その蝶に導かれて、ナヤタは仲間の救出の旅に出るのだが……
次々に迫る危機と、それを助ける存在、「左目」の謎と課せられた使命……と、諸々の配置はまさに模範的。
じつに優等生的な作品だが、これを受賞作に押し上げたのは、絵画的なイメージの豊かさと、エコロジーや戦争などの問題を提起しながら、教訓的になっていない点だろう。
じつに「物語」に誠実で、それが読後感を感動的なものにしている。
作者・深月ともみさんは創作サポートセンターの優等生である。
今後の活躍を期待いたします。
(2010.4.19)
[SF HomePage] [目次] [戻る] [次へ]