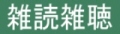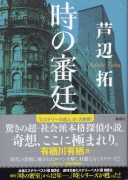2012年の年間日本SF傑作選
おなじみの年間傑作選。
宮内悠介、上田早夕里、円城塔、瀬名秀明……と、勢いのあるSF作家に加えて、(おれとしては初めて読む)乾緑郎、會川昇(脚本である)、平方イコルスン(マンガである)の異色作など、このような形でなければ知らないままだった可能性が高く、SFもここまで拡大しているのかと驚く。傑作揃いで、どれから読んでも面白い。
ここでは第4回創元SF短編賞の受賞作、宮西建礼「銀河風帆走」について。
この賞はここ数年、有力な書き手を誕生させてきたが、「銀河風帆走」も今後を期待させる傑作だ。
10億キロの距離をおいて旅する「ふたり」の人工知性体。中型の船ほどの金属製楕円体で、内部には人類を含むすべての生物種の遺伝情報が詰め込まれている。(遠い未来に)地球が消滅することを知った人類が作り上げた装置で、1600年前に作られ、ごくごく希薄な恒星風を巨大な帆に受けて恒星間を旅する。向かうは超巨大ブラックホールからジェット流が噴出する銀河中心核……。
たいへんな設定だが、ともかくその語り口が素晴らしい。
ここには「人間」はひとりも出てこない。時間スケールも空間も人間の寿命を遙かに超えた「別階層」にある。知性体は(人間でいえば)男と女の性格を獲得しているが、交信するだけで片道1時間を要する。
ところが、ふたりは「タンポポ」の話題を、ドライブしながら会話するような感覚でつづける。
銀河系スケールでの進行を「人間の日常感覚」に翻訳しつつ語る方法である。これが見事にうまい。
たとえば、核融合ブーースターによる加速が終わってそれが投棄されると「ぼくの身体はずいぶんスリムになった」とか、10億キロ離れての交信が「会話は文通に近くなる」とか(文通なんて今や死語だが)、こうした表現があってこそ、やがて姿を現す「鏡像物質」や銀河の「解体者」、さらには銀河間をつなぐ「橋」の大きさ・凄まじさが「生理的」に伝わってくる。
わが持論だが、宇宙SF最大の魅力は「新しい天体」と「階層を超える試み」にある。
ここでいう階層とは、地球重力圏〜太陽系〜銀河系〜大規模構造である。「銀河風帆走」は、銀河中心核の描写で「新しい天体」を、後半の展開で「階層超越」を、見事に達成している。(微少なタンポポの種子に関する描写が効果をあげていることはいうまでもない)
作者は種子島へH2打ち上げを見に行くほどの「現実の宇宙開発」ファンでもある。
しかも20代前半の若さ!
今後、種子島から130億光年彼方まで、宇宙の階層を物語でつないでくれるのではないか。期待は大きい。
(2013.9.8)
異形の天才降臨!
いやはや、なんというべきか、ともかく酉島伝法さんの異形世界がついに刊行された。
まさに「降臨」である。
表題作の創元SF短編賞受賞が2年前。この時にゲスト選考委員を務めたが、ともかくそこに描かれた異形の世界と特異な造語感覚に仰天した。「原色の想像力2」に掲載された第2作「洞の街」(これは今年の星雲賞候補になった)で世界を広げ、第3作「百々似隊商」では、さらに(この文体で)魅力的なキャラクターを創り出し、(この文体で)ゴミダメの上にひろがる青空のような、不思議な詩情まで感じさせる。
ここに書き下ろしの「泥海の浮き城」(ここでもハードボイルド調という実験が行われている)を加え、5篇の「断章」でつないだ構成である。
こうして一冊になったことで(巻末の大森望氏の解説がこれまた秀逸である)酉島氏の描く異形世界の全体像が見えてくるのだが、2年前に「皆勤の徒」を読んだときには想像もしていなかった背景が浮上してくるのである。
(2年前の選評では、ブラック企業の労働者を描いたという解釈もできるといったことを書いているが、そしてむろん誤読ではないのだが、もっと深いところから発想された世界であることがわかってくる)
ついでながら、作者はイラストレーターでもあり、本文中の挿絵も素晴らしい。
が、表紙絵は加藤直之さんで、これがまた「目つき」といい「ぬめり感」といい、凄い迫力である。
本年度最大の問題作であろう。
(2013.9.8)
森下一仁『小松左京の「文学」』(小松左京マガジン50巻)
小松左京マガジンが50号で一区切り(終刊)となった。ぼくも幾つか記事を書かせてもらったし、米朝師匠出席の座談会に同席させていただいたり(「題なし」座談会(←「桂米朝集成」に収録)の構成は吾輩であります)、思い出も多い。
この最後の2巻(49、50号)に掲載された森下一仁氏の評論「小松左京の『文学』」は、数ある小松左京論の中でも屈指のもので、最後にこの評論を得た意義は大きい。
森下氏の評論は前後二部構成で、49号「迷路の果てに」、50号「廃墟空間から複素宇宙へ」に分かれる。
前半は青春時代、戦争体験、いわゆる文学修行の時代(迷路)を経て「地には平和を」を応募するまでの時代。後半は「地には平和を」が評価され、作家デビューから最後の作品「虚無回廊」までの軌跡である。
この後半の章には、今ごろになってだが、蒙を啓かれるというか、目からウロコが数枚落ちた。
そのウロコ数枚(個人的メモ)を記録しておきたい。
小松作品の出発点が戦争による焦土、廃墟にあることは「地には平和を」「日本アパッチ族」から明かで、小松さん自身も何度も発言している。
印象に残っているのが70年、クラークとの対談(小松左京マガジン26巻に収録)である。ほとんど最後になって、小松さんはクラークにこう問いかけている。
戦争で焼け野原になった都市を見て「『惑星の肌』みたいなものを感じられた……その時「文明」と「地球」というものを同時に見たような気がした」……そこから、科学とSFから、科学がいずれ突き当たる「哲学的」「文学的」問題にまで質問を進める。
クラークは「複雑な形而上学的な議論になってきた」と、ちょっと戸惑っている。
ぼくはこれをテレビで見ていて、足元の焦土(廃墟)を見つめていた立場とレーダーの横で宇宙を見上げていた立場、ありていにいえば戦争に負けた方と勝った方の「姿勢」の違いかな(何しろ26歳の時である)程度に考えていたのである。
小松さんが「廃墟」でなく「廃墟空間」と表現している意味に森下評論で初めて気づいた。64年(デビュー直後)から使われているのだった。
この「廃墟空間」が小松SFの出発点にあった重要キーワードとすれば、その後の「虚無回廊」につながる重要キーワードが「複素空間」(森下さんは「複素宇宙」とまとめている)である。
これも小松さん独特の表現である。ぼくが最初に気づいたのは80年頃で、初出が何だったかが思い出せない。何かの文庫解説に「物語を複素空間に展開する」という表現があって、数学的展開をいうなら「複素平面」が正確なのではないかと思ったことがある。わが読みの浅さを自覚したのは、森下さんも引用している「科学と虚構」(91年)を読んだときで、小松さんが「虚数」から得たイマジネーションがかくも深いものかと驚いた(これが「虚無回廊」のタイトルや章の番号につながる)。このことは、その後、小松さんを挟んで福江純さんと並んだセミナーで話題にしたことがある。わが「『函数論』は道具として使ってきたから、複素数にそこまでロマンが感じられない」に対して、福江さんから「それはおそらく工学部と理学部のちがいでしょう」と指摘された。
廃墟空間→複素空間のつながりで、これまで幾つか小骨のようにひっかかっていた問題がいっきょに氷解した。
おれは表面(平面)しか見てないのに、御大は最初から時間軸まで含む広がり(空間)を透視しておられたのである。
久住昌之×谷口ジロー『孤独のグルメ』(扶桑社文庫)+「野武士、西へ」
今ごろ……だが。
週刊朝日編集長セクハラで解雇のニュースで、ハシシタ事件がちょうど1年前だなと思い出したら、この日に『孤独のグルメ』というテレビドラマ(?)をたまたま見ている。
これが面白いといったら、東京ではかなりの人気番組で「原作」があることを教えていただいた。
そして先日、友人が文庫化されていると送ってくれた。
なんと初出は94〜96年にマンガ誌連載で、通読して、1編は喫茶店かどこかで読んでいることを思い出した。
なんとも息の長い作品だ。
20年前の作品だから、店は変わっているところが多い(はず)。唯一の「大阪」で取り上げられている「中津のたこやき」は、わが穴蔵から徒歩3分の屋台だが、諸々の制限から、十数年前には姿を消している。
テレビのは続編というか、新規に訪れた店なのであろう。
巻末に久住氏のエッセイがあり、初めての店に入る時の緊張と勇気に触れられている。迷った挙げ句、おずおずと入るのに対して、理想の入店姿勢は、ガラッと戸を開け、ズンズン店の中に入り、ドカッと座って、店主に「オヤジ、飯だ」と怒鳴る、時代劇に出てくる「野武士」だという。
このエッセイが文庫版に添えられたものとしても2000年、もう13年前である。
そして、久住氏の最新刊のタイトルが「野武士、西へ」(集英社)なのである。姿勢にブレがないなあ。
これは雑誌連載時に読んでいる。東海道を2年かけて「散歩」する。野武士に憧れつつも、やっぱり井之頭五郎であって、そこいらへんの店に入って食べたり呟いたりして移動していく。
おれが同志的共感を覚える(ファンのほとんどがそうであろう)のは「東海道踏破」にチャレンジしながら日常通りのことをやっている姿勢で、つまり「非日常的な状況で普段と同じことをする」のが好きなのである。
旅行に行っても、名所旧跡ではなく、地方都市のそこいらへんをウロウロするのが好き。
おれの「早朝グルメ」も、時間帯を非日常にシフトしただけで、やってることは会社帰りのサラリーマンと同じなのである。
久住氏とは一度飲んでみたいなあ……と思いつつ、もしどこかの居酒屋で偶然いっしょになったとしても、気づかぬまま、カウンターでちょっと距離をおいて、黙って飲んでいるだけだろうな。
森川弘子『沖縄 屋久島 お値打ち旅』(メディアファクトリー)
SF作家クラブ50周年がそろそろ終わろうとしている。
実現しそこねた企画をひとつ。
さる筋からの話があり、沖縄観光と連動して何かやれないかと某所で某委員たちと相談したことがある。
その時のわが提案のひとつが、
「北野勇作一家に沖縄に1ヶ月ほど住んでもらって、モリカワに作品にしてもらう」
であった。
コストは安いし、われながら名案だと思ったのだが、なんと、それに近いことはすでに実行されていたのである。
「年収150万円一家」以来、モリカワは快調である。
この本が話題になったとき(もう4年になるのか)、旅行編やレシピ集などを期待したのだが、その後、モリカワは見事に期待にこたえてくれている。
『年収150万円一家 毎日のこんだて』は写真入りのレシピ集で、見事に安くて旨そうなのばかり。
パンの耳利用のカナッペなど、じつに白ワインに合いそうだし、大根の葉っぱと揚げを炒めたのはウチの専属料理人も前から好きで、葉っぱ付きの大根を天満ぷららまで買いに行ったりしていた。
この本のおかげでウチでも(コストダウンは別として)メニューがさらに増えたものである。
『年収150万円一家 節約生活15年目』では、さらに数々のテクニックを紹介。
『森川弘子さんちのくすくす子育て』は心あたたまるイラストエッセイ。
本書『沖縄屋久島お値打ち旅』は『身の丈海外旅行inベトナム』につづく旅行記である。
ベツナム編も、料理が多彩だし、へんなガイドが登場したりで面白い。
今度は国内旅行である。
やっぱり「150万円一家」らしく、格安航空券の手配から搭乗手続きなど詳しいし、渚で手に入れる貝や小動物の描写も豊かで楽しい。
意外なのは森川北野勇作さんがレンタカーを運転するくだりで、勇作氏といえばボロ自転車が定番だから、レンタカーが意外に感じたが、かめくんはフォークリフトの運転に習熟しているのだから、クルマの運転もお手のものだったのだ。
場所が場所だけに、おれの苦手とするS字型が出てこないかヒヤヒヤしたが、ほっ。
旅行中、一度も見なかったのかなあ……
芦辺拓『奇譚を売る店』(光文社)
ちょっとした本好きなら、商店街の路地裏などで古本屋に出会うと、ちょっと胸がときめく。
ひょっとしたら積み上げてある雑誌の棚に掘り出し物(たとえばSFマガジンの丸表紙とか)があるのではないか、とか。
いや、子供の頃、読みたくても手が出せなかったエロ雑誌(おれの場合「100万人の夜」なんかだが)があるかもしれない。
だが、そんな場所で手にした本には、恐ろしい魔が潜んでいるのかもしれないのである。
芦辺拓氏の『奇譚を売る店』は、そのような本好きを震え上がらせる「古書ホラー」である。
ここに森江春策は出てこない。語り手「私」は古書好きの、あまり売れない推理作家である。
「私」は偶然見つけた古書店で、奇妙な古書を見つけ、少し迷うが「また買ってしまった。」ということになる。
それは古い「脳病院」の入院案内であったり(そこには詳しい図面があったため、その模型を作ることになるのだが……)、奇想小説の名作の「幻の映画化資料」であったり……
6篇中、おれがいちばん怖かったのが「這い寄る影」。
昭和30年頃には、まだ「猟奇雑誌」があった。正規の書店にはなく、貸本屋の一角に、エロ雑誌や実話雑誌と並べて置いてあった。借りる度胸はなく、他の本と一緒に手にして盗み読みしたものである。むろん全部は読み切れない。挿絵を見て、数頁を速読して、急いで棚に戻したものである。そこには恐ろしくもグロテスクな猟奇事件が展開されているような……気配があった。
「私」が手にしたのは、そんな猟奇探偵小説のアンソロジーなのだが、組み方は統一されておらず、どうやらその作家は自分の著書を出せぬまま、雑誌掲載作を集めて製本したらしいのである。
「私」はその自家製本の古書を買って読み始めるのだが……
いやあ、恐ろしい。中学時代の、あの怖いもの見たさ感覚をこの歳になって味わうことになろうとは。
ちょっと読者を選ぶ作品かもしれないが、芦辺さんの古書好きとホラー志向が融合した怪作だ。
芦辺拓『時の審廷』(講談社)
ハルビンは今や濃密なPM2.5で死の街寸前だが、ミステリーでは伊達邦彦の生誕地であり、それより前には伊藤博文が暗殺された街である。満州国建国後は鉄道の要衝であるとともに、謀略渦巻く魔都となった。
現近代ミステリーでは南の上海と並ぶ魅力的な舞台である。
「時の審廷」は戦前のハルビンと戦後日本と現代を結ぶ壮大なミステリー、「時の密室」以来の「時」シリーズ第3作である。
・開戦寸前のハルビン。若い遊軍記者和智は路上で死体を発見したことから、不気味な一家失踪事件に巻き込まれる。恋心を抱いていた美少女タチアナが関与しているらしい。彼女は白系ロシア貴族の末裔である。
・戦後日本。鉄道総裁の礫死体が発見され、一方、持ち込んだ青酸カリで銀行員を大量死させた容疑者の画家は「幻の春画」を描いていたらしい……
・現代日本。総選挙の結果、政権が交代しようとしている。その寸前「東海地震予知情報」が出され、日本は一種の戒厳令下に置かれた。
そして、森江春策は奇妙な電話を受け、「日本分断」という言葉を聞く……
いやはや、壮大な設定である。
「時の密室」が明治の川口居留地と現代大阪にまたがる「巨大密室」だったのに対して、「時の審廷」は、舞台が国際的に広がり、事件は70年の時を超え、戦後の有名事件との関連あり、ちゃんと「密室」もあり、日本の根幹を揺るがす謀略あり、しかもひと筋のロマンスもあり……これが森江の手でつなげられ解明されていく。
ミステリーだから、これ以上は書かないことにしよう。
ともかく、この「時」シリーズは、芦辺さんにしかやれない大業だろうなあ。
本書の「序章」が発表されたのは2010年春という。出版まで3年以上を要した事情は冒頭で触れてある。
作者の時代感覚が一種の予知として働くことはあり、これは事件を素材に待ってましたと作品化する姿勢とは対極にある。作者の才能というべきだろう。
この作品を読んでいる最中にある事件の関係者が亡くなるなど、不思議なシンクロニシティを覚えたほどである。
小佐田定雄『枝雀らくごの舞台裏』(ちくま新書)
枝雀師匠には今も熱心なファンが多く、高座の細部まで覚えていて議論する人が多い。
先だっても「猪買いの構え方間違いバージョン」というだけで、枝雀寄○回目のでしょうと、ちゃんとビデオに残していた人(知人のSFファンである)がいたりして驚いた。
その極めつけは小佐田定雄氏であろう。
小佐田さんはマニアというよりも、ある時期は座付き作家であり、「弟子」とは別の距離感でいっしょに歩んで来た人である。
そんな立場の作家が枝雀師匠の持ちネタに沿ってエピソードを披露しているのだから、面白くないはずがない。
枝雀師匠の落語の記録は、活字、レコード、テープ、CD、DVDなど、全部で25種類(シリーズ)あるという。個人録画やネット情報は膨大。
同じネタでも時代と場所でどう演出が変わったか、資料の索引までつけて、細かく解説してある(読者はその気になれば記録で検証できるわけだから、よほどの自信がなければできることではない)。
演じ方について師匠本人がどう語ったまで、初めて知ることが多くて、ものすごく面白いのだが、同時に、ちょっと息苦しくなるのも確かだ。その理由はかんべむさしさんがこちらの3013年9月のところに長文を書かれている。
さすがにおれはそこまでは考えない。日頃から「笑いとは」なんて考えてないし、体質の違いもありそうだ。
おれが一番面白いと思ったのは談志との関係である。
談志(家元)は枝雀(師匠)と議論したかったらしい。が、師匠は「わたい、理屈が苦手ですねん」と避けたという。
師匠没後、家元が小佐田氏に「おれが助けることはできなかったのか?」と訊き、小佐田氏は「無理やったと思います」という。
その理由は、
「家元は悪いことがおこったら全部ひとのせいにしはるでしょう。枝雀さんは全部自分が悪いと思わはります。多分、お互いに理解しあうことは無理やったと思います」
至言である。
ふたりは「業の肯定」対「緊張と緩和」と、落語の定義を考えつづける点で似ていて、性格が正反対だったのである。
小佐田氏は(家元/師匠を)ポジとネガ、太陽と月、ひとのせいと自責としているが、おれなりにつけ加えれば、支配型と孤高型、テーマ優先と芸風優先、誇大妄想と被害妄想、ホラと謙遜、SとM……まだまだあるな。
どちががいいとか悪いとかではないですよ。もうひつと追加すれば、没後、家元は本が売れ、師匠はCD・DVDが売れる…の差ではないか。
手間と時間がかけられた新書である。
落語本というのは2、3ヶ月でチャカチャカと仕上げて一丁上がりでは書けないのである。
あ、落語本に限らんか。
[SF HomePage] [目次] [戻る] [次へ]